院長ブログ
-
生理の貧困
2021年3月7日|院長ブログ
「生理の貧困」が最近ニュースで話題になりました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210304/k10012896501000.html
「生理の貧困」を調査 学生の約2割“生理用品 買うのに苦労” | 新型コロナ 経済影響 | NHKニュース
コロナ禍で経済的に苦しくなり、満足に生理用品が買えない状態のことを指します。
生活費の多くをバイトに頼っていて、コロナ感染症による時間短縮営業などで飲食店等での仕事が減ったことが影響しているとか。
私は仕事柄、毎日「生理どうでしたか」を話題にしています。いろんな生理の話を聞きます。しかしナプキンが高くて買えないという話は聞いたことがありませんでした。買えない値段でもないと思iいましたが、これすら買うのにお金がない、ということでしょうか。
出血している日数は3日から7日、周期28日を平均として25日から38日の間、というのが正常の月経です。
規則正しく月経が来ていることが体の調子が良い証拠といわれていましたが、最近 専門家の間では、必ずしもそうではない、といわれます。
近代化以前(150年前くらいまでの)の女性は10代半ばで妊娠可能な体になると、10代後半で結婚、妊娠・出産を繰り返し、平均寿命は50歳くらいでしたから、一生の間に経験する月経の数は、現代よりはるかにすくなかったと考えられています。
イギリスのピルの参考書に書いてあったことですが、1950年代ごろ、イギリスからアフリカのある国にボランティアで行った医師が、40歳のある女性からこんな相談を受けたそうです。
「下からなにか変な出血があるんですけど・・・」
出血の出方からすると、どう考えても生理。よくよく話を聞いてみると、その女性は、10代半ばで妊娠してから、出産して授乳、何年かして排卵がもどると、すぐに妊娠、ということを繰り返し、11人の子供がいるが、なんと、40歳になるまで生理を経験したことがなかったそうです。
近代化以前の社会では、女性は妊娠と出産を繰り返し、寿命も短かったので、一生の間に生理を経験する回数が 今ほど頻度が多くなかったと考えられています。
毎月毎月 月経を経験しつづけることで、子宮内膜症の頻度も昔より増加しているのではないかという説があります。

最近「男性の体」がイヤで女性の体に性転換したいという人の話を聞きますが、そういう人は生理のトラブルも経験したいのでしょうか。
生理の量や痛みに個人差はありますが、少なくとも「楽しい生理」はないようです。
私の外来で見かける「生理でびっくり」には以下のような事例があります。
*彼氏とエッチしたけど妊娠すると困る、生理が来ない、妊娠かなあ、どうしよう、どうしよう、やっと来た、というような「ほっとした生理」は時々耳にします。
*最後の生理いつだったかなあ、生理来ないんですけど・・・えっ? 妊娠してるって? うっそお! とびっくりされる人は一年間に2~3人見かけます。
生理の時に何を使っているかについては、印象ですが、ナプキン(とおりものシート)8割以上、タンポンは1割くらいでしょうか。
さて、高いと言われるナプキンですが、もっとエコな月経時のものがあるのをご存じでしょうか。
月経カップといって、月経血をためるシリコン製のカップが市販されています。3000円から7000円くらいでネットで市販されています。
(Amazonのサイトから)

私も産婦人科医ですので、試しに買ってみて、周りの女性に試してもらったことがあります。やわらかいシリコン製で、洗えば何回でも繰り返し使えて、とってもエコです。ただ初めてモノをみた人によれば漏れないか不安、指でまげて出し入れしますが、慣れるまでちょっとコツがいるようです。膣の大きさも結構個人差が大きいので、自分のに会うサイズを見つけるのも大変かもしれません。体質や、お産の経験のあるなし、性行為の頻度などで膣の大きさは人によって違いが大きいです。(S・M・Lというおおざっぱな分け方だと、サイズが合わない人がいるかもしれません)
ナプキンが高いという話だったので、月経カップもどうかな、というお話でした。
-
ふんどしの日
2021年2月17日|院長ブログ
2月14日は何の日かご存知ですか?
もちろんご存じですよね。
そう・・・2月14日は
_
_
ふんどしの日です。
日本古来の文化であり、伝統的な下着の「ふんどし」。2と14で「ふんどし」と読む語呂合わせから日本ふんどし協会が制定しています。
ちょっと前に「女性用ふんどし」も流行しましたね。
むれやすいショーツとは違って、肌を締め付けないので、肌荒れを起こしやすい人、膣炎をおこしやすい人にはお勧めです。

ふんどし女子
この冬場、気温が低いことも関係するのか、肌のトラブルも多いです。
肌のトラブルと言えば皮膚科、と思うかもしれませんが、陰部の肌トラブルに限っては、皮膚科に行くのは気後れするという理由で婦人科を受診します。
皮膚トラブルの対応では、体の部位に関わらず、1)刺激になるものを避ける、2)肌の保湿(うるおい)を大事にする 3)睡眠を十分とってストレスを避け身体の免疫力を上げる ことが基本です。
清潔にしようと、強い洗浄剤で洗いすぎると、むしろ皮脂を落としてしまい、かえって痒みをひどくしてしまっている人もいるので、洗いすぎないように気をつけましょう。
陰部専用の洗浄剤(http://www.lactacyd.jp/)もあります。
保湿効果があり、痒みを取る薬としては、1)ワセリンなど単に保湿をするだけのもの
2)尿素系は角質を軟らかくして水分保持させるもの 3)ヘパリン類似物質といって水分保持と同時に血行も促進するもの、などがあります。
ワセリンはいくら使っても副作用ないですが、他のものは医師に相談しましょう。
さて、ちょっと変わった下着で以前流行(というかメディアで取り上げられた)したものに
男性用ブラジャー
というのもありました。

楽天の販売サイトより
こんなもの、どうしてつけたくなるのか・・・
と思っていたのですが
私もマラソン大会で走った時、着ているシャツによっては乳首がすれて痛くなることがあり、役に立つかもしれない。
絆創膏貼って代用してますけど。
-
試験の季節
2021年1月27日|院長ブログ
 この時期受験のシーズンですね!
この時期受験のシーズンですね!以前ネット上の掲示板に出ていたネタですが、笑えたので転載します。
《 中国人の日本語試験とその回答 》
問1:「 あたかも 」を使って短文を作りなさい。
答: 「冷蔵庫に牛乳が、あたかもしれない。」
問2:「 どんより 」を使って短文を作りなさい
答;「 僕はうどんよりそばが好きだ。」
問3: 「まさか~ろう」を使って短文を作りなさい
答: 「 まさかりかついだきんたろう。」
問4: 「もし~なら」を使って短文を作りなさい。
答: 「もしもし、奈良県の人ですか?」
問5: 「うってかわって」を使って短文を作りなさい。
答: 「彼は麻薬をうってかわってしまった。」 笑える!
-
清潔 不潔
2021年1月24日|院長ブログ
コロナ感染症がなかなか収束しないですね。
マスクしてさえいれば良い、と思っている人が増えてきたせいでしょうか。
換気と並んで重要なのは、接触の機会を減らすこと。
気が付かないうちに自分の顔に手が触れている、ことが以外にあるようです。
医療の現場では、手術や感染症の現場では、手洗いをして、手術着や予防衣を付けた後「余計なものにやたらと触ってはいけない」状態になります。
テレビのドラマで手術中に「汗拭いて」と言って助手に汗を拭かせる外科医がいますが、あればエラそうにしているわけではなくて、自分の顔を触ると手が不潔になるからです。ちなみに手術室で使う「不潔」とは「清潔(滅菌されて感染のリスクのない状態)ではない」という意味で、一般に使われる「汚染されている」という意味ではありません。
「ちょっと顔のここんとこ掻いて」
「ずれたメガネ直して」
なども手術中に自分の顔を触れない外科医が出すリクエストの一つ。
手術に加わっている医師で、操作をしていない手はどうしているかというと、滅菌されたドレープ(手術野を覆う布)に手をおろしていることが多い。

*
私が以前勤めていた大病院で、ある有名な外科医と同席して手術をする機会があった。
手術の腕はたしかに上手で、ずばずばと目標の臓器に達して、最小限の傷で患部を摘出する。
そして要求することも厳しい。
「そこ!不潔だから触るんじゃない!」
としかりつけながらも、てきぱきと手術の手は動いて、順調に手術が進んでいった。
緊張する手術の山場を越えて手術も終わりに近づいたときだ。
小さく
「イヤーン」
と若い女の声がした。
外科医の横にいる機械出し(メスや鉗子を出す役割をしている)の看護師の声。
鉗子を取りに手を伸ばすフリをして、そおっと若い看護婦の手を握ったのでした。
「先生!そんなとこ触らないで下さい!」
横にいた年配看護婦からたちまちヤジが上がった。
その外科医は手術は早いのですが女にも手が早かった。
-
温度設定をめぐる葛藤
2021年1月13日|院長ブログ
職場の温度設定。
オフィスで仕事をしている人なら誰しも経験しますが、室温が「高すぎる」とか「低すぎる」と感じることはないですか? 市役所とか「夏は28度まで」と公表しているところは別ですが、決められた温度がなくて、リモコンの温度を上げたり・下げたり ってことはないですか?

冬場でもこれ以上暖かくしちゃダメだよな、という考え方の人もいる
夏場で、エアコンの設定温度もしょっちゅう変わる(というか、私はちょこちょこ変えている)のですが、冬場もよく変わります。とくにこの冬、感染症対策には「換気をよく」するため、窓を開けるようになりました。
病院は病人のことを考えて、冬でも暖房がよく効いて暖かいのですが、総合病院などでは24度くらいまで上げているようです。
私のクリニックではいつもの冬は、病棟は24度、外来診察室の設定温度は22度くらいまでにしています。
しかしこの冬は違う。
ヒューヒュー寒い風が入ってくる。
内診する場所で、下着をとった人のところにも風が入ってしまうので、申し訳ないと思いながら、でも感染予防も大事と思ってあえて窓を開けています。

冬場だったらこれくらい暖かくしなきゃ、と思っている人もいる
夏は夏で、冷房の効き目をどの程度にするか、はっきりした根拠はありません。
そうなると、エアコン温度の設定は、
1)中の人が快適と感じる温度
2)外気と温度差が大きすぎると健康によくないので、エアコンは効かせすぎない
3)節電も考える
などの要素のほかに
4)(うちのような医療機関では)患者(とくに新生児)のためには暖かめにしておく
(どの程度が暖かめか、は人によって意見が違う)
5)発言権の大きいスタッフが決める
6)リーダー(つまり院長である私)が決める
など種々の要素があります。
私の考えは、なるべく外部環境(自然)に近い状態で身体機能を損なわない程度にしたいのですが、たぶん全体の意見の総和ではない。
暖房の効きすぎたところ、冷房の効きすぎたところに長時間いると、体の自律神経機能に影響がでる、と心配しているのは私だけなのかどうか、自説を主張できる根拠もありません。あからさまにやると「この院長はいちいち温度にうるさい」と思われるので一人の時にちょこちょことリモコンの温度設定を変えたりしています。
リモコンの温度設定、
上がっていたら・下げる 下がっていたら・上げる
上がっていたら・下げる 下がっていたら・上げる
上がっていたら・下げる 下がっていたら・上げる
・・・
延々とやっています
-
ショウガは役に立つ!
2021年1月11日|院長ブログ

これは生姜でしょうが
寒い季節になると、ショウガを目にすることが多くなります。
ショウガ湯、ショウガ入りアメ、ショウガ風味の菓子。
ジンジャー・エール、ジンジャーブレッド、いろいろありますね。
「体を温める」として日本では知られていて、
冷え性に効果があるといわれています。
効能を信じている私は、ジンジャラー(生姜の信奉者をこう呼びます)の一人です。
東洋医学でも生のショウガを「生姜(しょうきょう)」、乾燥させてショウガを「乾姜(カンキョウ)」と呼びそれぞれ違う作用と呼ばれ漢方薬として使われます。
古代ギリシャの薬の本にも記載されており、欧米でも古くからハーブとして知られています。
イギリス国王ヘンリー8世がペストの予防に役立つとして国民に広めたのがきっかけで、ジンジャーブレッドが食べられるようになったとか。
ショウガの成分にはジンゲロールなどが含まれ、血行改善、体を温める作用があるとされています。成分の一つジンゲロンは基礎代謝を高めて脂肪の燃焼を促進するダイエット効果も知られています。
そのほか、殺菌効果があり、下痢の治療に使われたり、
蛋白分解酵素の働きのため、肉をやわらかくする働きもあります(豚肉のしょうが焼きはおいしいね)。
現在の欧米では乗り物酔いの吐き気止め、片頭痛、つわりの治療として役に立つとされていて、リウマチや関節炎などの治療にも用いられているそうですが、
なぜか
日本で広まっているように、体を温める効果についてはほとんど文献に記載されていません。
日本は神道の国で、神社(ジンジャー)があるからか?
ショウガない話ですみません。
-
サンタの帽子
2020年12月27日|院長ブログ
この数日、一時的にお産の件数が増えました。寝不足気味。
産婦人科での仕事は、他の診療科と比べると、ハッピーであるといえます。
老人の病気を扱うほかの診療科と違って、
唯一「おめでとう」といえるから。お産の進み方は早い人もいれば遅い人もいるのですが、生まれてくる赤ちゃんは
狭い産道を通ってくるので、頭の形が変形して縦長になっていることもあり、お産に長時間かかった場合には、後頭部が盛り上がって生まれてくるような赤ちゃんもあります。
出産直前まで来て、お産が止まって長時間経過してしまっている状態の時には点滴による陣痛の誘発をしたり、吸引分娩といって、胎児の頭を牽引して、体外に出す操作を行うこともあります。
吸引分娩は、簡単に言うと、掃除機のホースのような吸引管の先に、トイレの詰まりを取るための吸盤のような器具や丸い金属カップがついた機械を使うのです。
骨盤をとおり、膣から出てくる胎児の頭は、大人と違って軟らかく変形しやすく、吸引分娩を何回かすると、出生後3日くらいまで吸引カップの形に頭が変形していることがあります。
生まれたばかりの赤ちゃんは、頭が大きくて、頭から体温が奪われやすいので
赤ちゃんの頭に帽子をかぶせて、体温が下がらないようにします。
私が総合病院に勤めていた10年くらい前の話です。
12月のある日、吸引分娩で生まれた赤ちゃんを見に行ったら、眺めたらサンタクロースの赤い帽子をかぶっていた。NICU(新生児集中治療室)のスタッフの粋な取り計らいでした。

「いやーん、可愛いー」
新生児室のベビーを見に来ていた、見舞い客の若い女性が声を上げていました。
私だけでした。
帽子の下に吸引分娩のでかいタンコブができているのを知っていたのは。
-
アフガニスタンの12月
2020年12月6日|院長ブログ
12月らしく寒くなってきましたね。
私、開業するずっと前は海外に出ることも多かったのですが、今回はアフガニスタンにいたころのことをお話します。
17年前の一年、アフガニスタン北部にNGOの医師として滞在していました。
緯度は日本の北関東と同じですが、乾燥していて雨が少なく、気温の変化が激しいところです。
夏には40度以上になるようなところですが、この年、大きな寒波が来て12月にはマイナス11度まで下がりました。
水道管が凍ってしまい使えなくなり、ガスも来ない、電気も数日停電続きました。アフガンはインフラが貧弱です。
私たちは、朝や夜はろうそくやランタンの明かりを便りにし、昼は自家発電機を回して通信機器や事務機器を動かさないと日本との定時連絡もとれませんでした。
一般の家庭には電気製品があまりないのと、停電が頻繁に起こる生活に慣れていて、あまりパニックにはなっていませんでしたが、滞在間もない私たちにとっては大変でした。
私は95年の阪神大震災で、冬季に電気や水、ガスの止まった状態で生活したことがありますが、アフガニスタンの方が過酷だった。
この状況を情報発信するメディアがないので、ニュースにならないだけですが、こういう寒さで絶対数十人単位で人が死んでいるはずです。
_

左端が私 アフガン人スタッフたちと(日本人3人)
アフガンで開設した診療所で患者をみていましたが、夏はマラリアや下痢が多い一方で、冬になると風邪や肺炎など呼吸器系の病気が増え、火を使うことが多いため、火傷の患者も多くなりました。馬に蹴られてケガをした人も冬季に多くなりました。
病気の人を治すよりも、自分が病気にならないようにするのが大変でした。
アフガンのこういう状況を経験すると、日本に帰ってきて、普通に暮らせることのありがたさをしみじみ感じます。
公園の蛇口から水が出る、停電しない電気がある。こんなことすら、うれしいのです。
-
プロの仕事
2020年12月2日|院長ブログ
私は医療に関してはプロですが、ものを作ることについてはシロウト(素人)です。
家具の修理をしてみて、自分がいかにシロウトか思い知らされました。
当院の病室のベッドの木製の部分が、長年使っていて、塗装がはげてきたところがあったので、思い立って、私が直すことにしました。
ベッド柵の一部に固いものがあたってへこんでいる部分もあります。1)パテを塗って2)やすりで表面を磨いて3)木の色と似た色のペイントで色を塗りなおして、4)ニスを塗る、ことで元通りになるのだ、とシロウト考えで始めました。
表面を磨く機械のことを「サンダー」と呼ぶのだと生まれて初めて知り、中古工具の店に行ったり、日曜大工の動画を見て勉強です。こういうときに動画は役に立ちますね。サンダーの動かし方とかヤスリの目の選び方とか、初めて知ることばかり。

ものづくりって楽しいです
ホームセンターで買ったパテを盛ったら、盛りすぎてしまい、ヤスリ(サンダー)をかけたら、でこぼこになったパテ以外のところを削り過ぎ、元あった塗装が必要以上にはげてしまい、似た色と思って買ってきたペイントの色が塗ってみたら全然違う色だったり、ニスが垂れて。塗りあとがかえって目立ってしまったりと、素人目にみてもわかるようなひどい仕上がりになってしまいました。
健康のこともそうですけど、あるレベル以上はプロにお任せしたほうがいいんじゃないかと感じた今回の補修工事でした。
-
味噌汁のみたいわ めっちゃ
2020年11月22日|院長ブログ
休日はたまに自分で料理したりします。
外食行くにしても、不特定多数の他人のいる環境では感染症リスクもありますから、やはり自宅にいるのが良い。
手抜きの度合いに応じて、手ごろなものが売られているのも良いですね。
たとえばチャーハン食べるにしても、1)炊いたご飯、焼き豚、ネギ、卵と食材をそろえて作る方法
から2)ごはんは、パック米、調味料はチャーハンの素を使うなどして、一部を手抜きする方法
から3)冷凍チャーハンを買ってきて、家ではレンジでチンするだけ
まで手抜きの度合いによっていろいろあります。
レシピといえば、かつて海外に滞在していたとき、私は現地の人にウケる日本食を作ろうと外国人にもわかる日本料理の本を現地で買いました。英語圏の人の書いた、「Cooking Japanese(日本料理の作り方)」の本です(写真)。
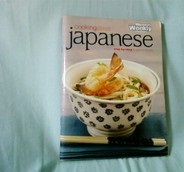
写真がきれいなので、まだ保管しています。西洋人の目で書かれた日本食の料理本だけに、日本人の私が読むと、けっこう面白い。
「do’s and dont’s of japanese etiquette(日本料理のエチケット)」というところを読むと、
「新しい割り箸や竹の箸を使うときはそれらを二つに割り、片方の箸でもう片方をこすって木のトゲをこそぎ取るようにすべし」と書かれている。
これって、悪いマナーじゃなかったっけ?
「熱い茶やスープ、麺類をすするときにチュルチュル、ズルズルと音を立てるのはアクセプタブル(acceptable:オーケー)である。
これは味わっているというサインであるし、熱いものを冷ますためである」
日本人は何気なくズルズルとラーメン食べるけど、あれって西洋人は気にするようですねえ。
この本には、日本人がよく食べる、寿司、刺身、味噌汁、そばの作り方が
載っていますが、名前の訳し方が面白い。いくつか紹介すると
「ツナ・ロール(Tuna rolls)」は「鉄火巻き」
ということはある程度想像がつく一方
「いなり寿司」は「seasoned tofu pouch(調味された豆腐の袋)」
と直訳される。
なんのこっちゃ?という感じである。
「煮込みうどん」は「individual udon casserole」である。
キャセロールは聞いたことあるが日本育ちの私は知らない。
「thick omelette」と書いてあるので
、
日本料理でもオムレツを作るのか、と思ってよく見たら「厚焼き卵」のことでありました。
「お好み焼き」は「savoury pancake」と訳されている。
直訳すれば「風味のあるホットケーキ」になります。
ここの作り方には
「アオノリは河口や湾の岩の上に成長する藻類から作られ、これを乾燥させ粉末にしたものが売られている」
と説明がされている。レシピーを読みながら、
(こんなもん、食うのかよ!)
と顔をしかめている読者の顔が想像されます。
岡崎体育のヒット曲「留学生」の歌詞で
「I messed up ,should’ve known last time I met ya (君に会った時にバカなことして後悔してる)」
が「みそしる飲みたいわ めっちゃ」と聞こえるのが笑えます。










