院長ブログ
-
ガマの油
2021年10月27日|院長ブログ
妊娠中に薬使って大丈夫か、という相談はよく受けるのですが、ステロイド剤も問い合わせが多い薬剤の一つです。
ステロイドはもともと「ステロイド骨格」を持つホルモンで、男性・女性ホルモンなども含まれるのですが、狭い意味では「副腎皮質ホルモン」のことです。
炎症をよく抑えるので、アトピー性皮膚炎、花粉症、喘息、コロナ感染など重症感染の治療、リウマチなど自己免疫疾患(膠原病)など用途はとても幅広く、病院ではよく使われる薬の一つです。
上手に使えばうまく症状を抑えますが、使い方が悪いと副作用がいろいろと出てしまう、「諸刃の剣」のような薬ですが、医師によって処方されているものであれば、治療上のメリットが大きいという判断なので、続けた方が良い場合がほとんどです。素人判断は避けましょう。
妊婦さんで、アトピーの治療につかう塗り薬、鼻炎や喘息で使うステロイドの吸入薬は問題ありません。
産婦人科で妊婦以外にステロイドを使う場面としては1)フェミニーナ軟膏など市販の抗ヒスタミン剤で効果がない陰部の皮膚炎、2)蕁麻疹 3)閉経した女性の外陰部の皮膚の萎縮にともなう痛み、4)カンジダ膣炎に抗真菌薬と併用して炎症を鎮める目的などにもよく使います。ステロイド剤は結構 いろいろ効いてくれるので助かります。
何でも効く塗り薬というと昔は「ガマの油」というのがあったのを知っていますか?

江戸時代までガマの油は「どんな傷にも効く万能薬」とされていたそうです。
ヒキガエルを鏡張りの箱に入れて、自分の姿を見させると、自分の姿に驚いて冷や汗(脂)をたらし、その油を集めて膏薬にしたものが「ガマの油」です。
https://www.youtube.com/watch?v=8bRltHqo7EI
私、大学生の頃、筑波山の近くにある某国立大学に在学していたことがあるのですが、高校時代の友人たちに、面白がって、お土産として売られていた、この「筑波山のガマの油」をたくさん買って、一人一個ずつ送ってあげたことがありました。ほんとに傷に効くのかわかりませんでしたが。
後で友人たちに聞いてみたら、気味悪がって、誰も使っていませんでした。
-
ユーレー山
2021年10月24日|院長ブログ
本日、久しぶりに遠出できる休みが入ったので、愛知県の山にのぼってきました。
第二東名高速道路ができて愛知県の東にアクセスがよくなったのですが、本日の目的地は新城市にある宇連山というところです。
宇連山は「うれやま」と読むそうです。英語にしたら「Ure-yama」。ニューキャッスル(新城)の「ユーレー山」です!
幽霊が住んでいそうです!
静岡県民は知らなかったのですが、ふもとに「愛知県民の森」という場所があり、そこから登っていきます。
昭和の時代に整備された施設と周辺のキャンプ場は、コロナの関係もあるのか全く人気がなく、そこはかとなく古さが漂っていて、それこそユーレイが出てきそうでした。
しかし、歩き出すと 空は晴天、風もなく、日差しも明るく、ユーレイのことはすぐに忘れて、気分上々で歩きました。
一歩一歩登っていくにつれて、気持ちが高ぶってきます。

ユーレイも煩悩もふもとに置いてきました
宇連山は割れやすい花崗岩でできた山で、登山道の浮いた石に足を乗せてコケたり滑ったり、大の大人が恥ずかしい恰好で転ぶのですが、誰も見ていないので安心です。
標高900mくらいの山ですが、急な斜面の岩場があるためか子連れの家族で来る人は少なく、山歩きに慣れた格好の少人数のグループや個人のクライマーとすれ違うだけでした。
比較的高齢の人が多いです。
去年この近くの山に登った時、山頂で、ある高齢者のグループが談笑中に、一人のおじいさんが
「(今までの人生で、仕事も趣味も)やることはやったし、あとは死ぬだけだあ」
と言っていたのが、妙に心に残っています。
-
人間ドック
2021年10月20日|院長ブログ
「人間ドック」という言葉を聞いたアメリカ人は
人間が鎖につながれて波止場にプカプカ浮かんでいるところを想像してしまうという。ちなみにDockといえば港の船着き場のこと,
「人間ドック」は和製英語で、日本でだけ使われている言葉らしいです。これではドザエモン(川に浮かんでいる水死体)じゃないですか、と一人でウケてます。
「人間ドッグ」と問診票に書いてくる人もいますが、これでは人面犬ですね。
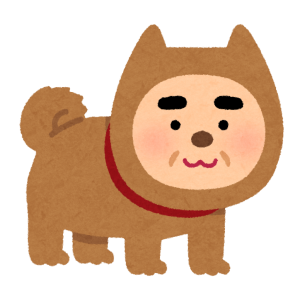
婦人科で行なっている健康診断(いわゆる検診)には子宮頚部がんがあります。
子宮頸(部)がんの検査も、単に細胞をとって終わり、という検診から、内診(双手診)で子宮卵巣の大きさに異常がないか調べる検診、エコーも併用する検診など様々あるのはご存じでしょうか。(今うちではエコーを併用したがん検診をしています。)
私が若いころ、アルバイトで「バス検診」に行ったことがあります。
バスの中に二つ内診台があって、カーテンの向こうから、交互にお尻が出てくるのです。
スピードは速いのですが、検査する私は、狭いバスの中、ずっと中腰を強いられ、しかも異常があるのかないのか、
ちゃんと内診もできないので非常にストレスで疲れるアルバイトでした。
膣の大きさもかなり個人差があって、お産の経験のある人に使う膣鏡をお産の経験のない人や帝王切開のお産の人にそのまま使うと痛みを伴うことがあり、神経使います。
*
卵巣がんの腫瘍マーカー(ガンがあると上昇する血液中の物質)を調べているところもあります。
子宮体がんの検査は、偽陰性といって、見落としの確率があるので、健康診断のスクリーニングには適していません。
以前は婦人科では子宮がん検診といっしょに乳がん検診もしているところが多かったです。
乳がんの検査は、現在では精度管理の点で触診よりはマンモグラフィーや超音波検査が勧められます。
さて昔は私も乳がん検診で触診をしていましたが、あるおばあちゃんの検診をしていた時のことです。
「わしみたいに70過ぎても乳ガンの心配することあるんですかセンセ?」とおばあちゃん。
「定期的にみたほうがいいですよ。どっかの牛乳みたいに、定期検査しないでほっといたら問題になることもありますから。」
当時、某牛乳会社が、賞味期限切れで汚染された牛乳を販売して問題になった頃の話です。

「わしの乳はもう賞味期限切れてるわ。ふぉっ、ふぉっ、ふぉっ」
-
初体験
2021年10月13日|院長ブログ
子宮頸がんワクチンの接種で一番効果が高いのは、性行為を経験する前の年代の人に接種することです。
10年以上前に子宮頸がんを予防するワクチンとして「サーバリックス」「ガーダシル」が使われていました。
浅薄なメディアによって「子宮頸がんワクチンをうつと副作用がある」との誤解が広まってしまい、日本では接種する人がほとんどいなくなってしまっていたのですが、その間に日本は世界の中で接種率の非常に低いワクチン後進国となってしまいました。
今、減りつつあるコロナ感染症が、ワクチンで予防できるという認識がひろがりました。この勢いに乗じて子宮頸がんワクチンも再開しようとする動きがあります。
良いことだと思います。
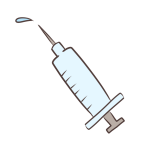
去年から日本で認可された新しい子宮頸がんワクチンは「シルガード9」と呼ばれますが、子宮頸がんに関係した9個のタイプのHPV(ヒトパピローマウイルス)感染を予防する効果があり、従来のもの(サーバリックスで2価、ガーダシルで4価)よりも広い範囲のウイルス感染を予防できます。現在、新しい「シルガード9」はまだ公費の補助がないので、価格が2~3万円と高いのですが、子宮頸がんを予防できるのなら、と接種希望者が出てきています。
当院でも先日、初めてこのシルガード9を接種することになりました。
ワクチンをうつ(接種する)立場の私がびっくりのは、手続きがチョー面倒くさいこと。
インフルエンザや風疹のような従来のワクチンは、問診票チェックして、問題なければすぐ接種できますが、このシルガード9は違いました。
1,接種する医者がワクチンの打ち方や後遺症についてオンラインで講習を受けておかないとうてない。
2.ワクチンを受ける人も自分のスマホ使ってオンラインで登録し、ワクチンをうった時間と場所を正確に記録に(サーバー上に)残す。
3.私のスマホで患者が登録されたかどうか確認する。
あらかじめ渡された分厚いマニュアルを前にしても、間違ったら怖いので、何もできません。

いろいろありすぎて何から手を付けていいのかわからず
マニュアルを探し回ったあげく(電話かけてくるな)といわんばかりに隅っこに書かれた0120のお問い合わせダイアルを2回電話しなおして、電話の相手に確認しながら、患者を目の前につれてきて、患者のスマホと私のスマホとつっつきあわせてデータ登録されたか確認。
確認できたところで、やっと接種となりました。うっちゃえば、あとは普通のワクチンと同様、しばらく経過観察の後 帰宅です。
あらかじめ渡されていたマニュアル全然役に立ちませんでした。
私も自分のスマホを患者に見せることはないのですが、今回は患者登録確認のため、患者のスマホと自分のスマホを見比べて、間違いがないようにびくびくしながら登録作業しました。
このワクチンは性行為の初体験の前にうったほうがいいワクチンですが、
私にとっても大変な「初体験」でした。
-
俊足(しゅんそく)
2021年10月10日|院長ブログ
秋で運動会のシーズンですね。
出産した後の健診で、赤ちゃんの名前を聞くことにしています。大事な親からのプレゼントである名前。男の子では最近「俊介」「俊太」「俊太郎」と「俊」という文字が入った名前を聞くことが多いです。
「俊くんかあ、いい名前ですねえ、きっと足が速くなるよ。俊足だから」
と、私は、相手が喜んでくれそうなことを言ってます。
子供用の運動靴で「俊足」というよく売れた靴がありますが、左コーナーで体が踏ん張れるように靴底が左右非対称になっているのが特徴だとか。
しかし「足が速い・・・」とか「俊足」という言葉を聞くと、私はぎくっとします。幼少期の心の中にトゲが刺さるようなトラウマです。
私は子供の頃、かけっこが遅くて、小学校の短距離走ではいつもビリ付近。運動会の駆けっこは苦手な種目の一つでした。短い時間に力を出しきる競技は苦手です。
自分では一生懸命走っているつもりでも、早く走れない。
 体力検査の50m走で力を出して、目をつぶって全力で足を動かしていたら、間違って隣のレーンに入って走っていたことも。
体力検査の50m走で力を出して、目をつぶって全力で足を動かしていたら、間違って隣のレーンに入って走っていたことも。人間、努力さえすればなんとかなると教えられて育ちましたが、短距離走など、努力だけではどうにもならないことを思い知らされました。駆けっこは勝敗がはっきりします。
その後の人生でいろいろ勝ち負けを経験しましたが、負けた人の身になって考えることができるのは、この「駆けっこが遅い」という経験からと思います。
パプアニューギニアのことわざに「努力だけでことが成るならば、オカマが子供を産むであろう」というのがあります(10代の頃知りましたが 実在するかどうか知りません)
競技系スポーツはキライだった一方、体を動かすのは好きだったので、「サッカーでボールを追いかけて、ただ走っている」
「ドッジボールでひたすら逃げる」 などはよくできていた気がします。大人になっても走ったり、逃げたりしています。
-
ヒゲ
2021年10月6日|院長ブログ
あなたはヒゲの男性、どう思いますか?
昨今、ヒゲを生やしている男性を見かけるようになり、ヒゲが市民権を得てきています。

ラマダンの後のやつれた顔
私は20年近く前、アフガニスタンに一年間住んでいたことがありますが、現地のイスラム社会では成人男性はヒゲをはやしているのが当たり前。
私もできるだけ現地の社会になじもうと、ヒゲを伸ばしました。 3週間もヒゲを剃らないでそのままにしておくと、段々とヒゲらしくなり
現地のスタッフたちは一様に 「おー、ドクター川島、カッコイイよお」
と誉めてくれました。 私はちっとも格好いいとは思いませんでしたが、みんなが誉めるので、しばらく続けてみました。
口ひげをたくわえてわかったことですが、夜寝るときなど、鼻息がヒゲにあたってわずらわしい。
トイレなどでこっそり鼻クソをほじった後(アフガンの街はホコリが多い!)や鼻をかんだ後でも、気がつかないうちに鼻クソがヒゲにこびりついていることがあり、(しまった!)と感じたことが数多い。
ミルクを飲んだ後でも、ミルクの白いのがいつまでもヒゲにこびりついていたこともありました。
毎週ヒゲをちょっとずつ刈りそろえないと、何もしない芝生のように、あっちこっちに向かってヒゲが伸びてきて手入れが面倒。
コップの水を飲むときに、水の中の大きなゴミをかき分けるフィルターの役目を果たすことはありましたが、それ以上の実用性はないことがわかり、すぐにヒゲをやめてしまいました。
アフガニスタンの男性どうしが出会うと、、まず握手ではじまります。 しかし、親しい間柄だと大の大人が男性同士で抱き合ったり、キスしたりします。
親しくなったアフガン男性に親愛の情を示されると、あごひげのジョリジョリ感が印象的です。
-
昔は大食いだった
2021年9月29日|院長ブログ
今年の健康診断を終えてほっとしています。
健康診断で常に指摘されているのが「コレステロールが高い」ところです。
やはり食習慣か・・・

たしかに、昔の私は大食いでした。
私が磐田南高生のころの話です。
ある日曜日、同級生と一緒に浜松の駅前へ出た私たちは 回転寿司の店で
「30皿食べたらタダ」
という看板を見つけました。
「やってみよう!」
僕たちは奮い立った。金はないが食欲だけはある。
30分で平らげなかったら全額払う、という規則のもと、
私たちはコンベアに乗って運ばれてくる寿司に果敢にチャレンジしていきました。
鉄火巻き、トロ、イクラ・・・
最初の10皿は難なくクリア。
納豆巻き、イカ、イナリ・・・
15皿を越えるころから満腹感が強くなってきた・・・
サバ、ウニ、ガリ、ガリ、ガリ・・・
20皿に近づくと、味わっているというよりは単に口に押し込んでいるだけ、
刺激を求めてショウガをやたらと口にする。
友人は20皿を越えたところでギブアップしてしまいました。
「食えねえ・・・」
彼は泣きそうな顔をしながらポケットから財布を出した。
当時の田舎の高校生にとってはイタい出費だ。
私は・・・あきらめませんでした。
ウニ、サバ、ガリ、カッパ巻き・・・
皿に乗せられて運ばれてくる寿司をひたすら口に詰め込んでいった。
・・・
25皿を越えたころから意識が遠のいてきました。
マラソンで言えば35キロ地点。
・・・苦しい
でもここであきらめたら寿司の代金を全部払わないといけない。
うっぷっ・・・
食い意地が私を奮い立たせました
目標の30皿を平らげたとき、
もう喉から出てきそう・・・
失神しそうな満腹感と 勝利の喜びにひたりました。
「ここに住所と名前書いてくれ」
寿司30皿分をタダにされた店のオヤジは
明らかに不機嫌そうだった。
(この店に二度と来ないでくれ!)
といいたげな顔でした。
****
数ヵ月後同じところを通りかかると
その回転寿司店はすでに廃業していました・・・
最近回転寿司屋に入って気が付いたのですが、スマホで予約でき、入り口の予約券発行機も変わりました。寿司はコンベヤで回ってなくて、タブレットで注文したものが送られてくるようになっています。
するすると入って さっさと食べて、 さっさと店を出る。自分たちがフォワグラのガチョウになった気がしました。
-
ネコに起こされる
2021年9月26日|院長ブログ
夜風が気持ちの良い季節になりました。
気持ちよく寝たいですね。
この快適な眠りを、最近さまたげるやつが出現しました。
私のヒタイをトントンとやわらかいものでたたく感触。ハッとして目を覚ますと、枕元にネコが!

みーこです。ふだんはツンツンしてます
うちのネコ、最近、夜中に私を起こすようになりました。
寝ている自分のオデコの部分を前足でポンポンとつつくのです。時計を見ると夜中の3時。
ネコは基本的にツンデレで、私になにかメッセージがあるとすれば「腹へったから食べ物くれ」か「外に行きたいから出してくれ」しかないのですが
明け方私を起こしに来るのは「外へ出せ」です。
私は眠りを妨げられてイヤなのですが、ネコも爪で引っかいたりとかではなく手加減しているようで
「起きてくださいよう~」
と遠慮がちにやっているような気がして
私は(しゃーない、ドア開けてやるか)という気になります。
私は体を起こすのも面倒なので、四つん這いになってごそごそ玄関の方向にはっていきます。
他の人から見たら四つん這いの私をネコが先導しているように見えます。
玄関まで行くと、私ががちゃっと、玄関のドアを開けて、猫を外に出してあげるのです。
幸い自宅の近所はイナカで周囲は茶畑ばかりなので、どっかの猫が歩き回っていても誰も文句は言わないのです。

食べ物と外に出る時だけ甘えてくる
私が朝食の時間になると、ちゃっかり外から戻ってきて「腹へったー」のネコなで声をするのですが、そういう時はどんなネコでも病みつきになるというあの「CIAO チュール」という餌を与えます。
このコロナ禍で人との接触が極端に減りました。
猫の肉球でつつかれる快感に目覚めてしまい、眠いながらも拒否できません。
-
月夜に思う
2021年9月22日|院長ブログ
夕方空を見上げたら、雲の合間に、満月に近い月。
いずこも同じ秋の夕暮れ
 ああ風流だな・・・
ああ風流だな・・・産婦人科医の私が「月」といえば思い出すのが月経。
人間の体は不思議なもので、月の暦と同じ28日で次の生理が来るようにできている、という話聞いたことありませんか?
しかし現実には、生理の周期は28日という人ばかりではありません。
25日で次の生理が来る、という人もあれば37日の周期の人もいます。
予定していた月経が来なくて、突然狂う、ということもよく起こります。
”日経よく読む”ではなくて”月経読めない”のです。クリニックには月経のトラブルで受診する人も多いのですが、環境の変化によるストレスで生理の周期が変わってしまうこともあります。
生理前の不快感、イライラなどの精神症状や胸の張り、胃腸の膨満感など体の不調が月経周期に一致して起こってくるものを「月経前(緊張)症候群(PMS:Premenstrual syndrome)」といいます。
月経周期の排卵後に起こり、黄体ホルモンが関係していると考えられています。
昔はこういうことがわからなかったので、
(男性にとっては突然怒りだす女性は理解不可能でした)
月の満ち欠けの影響でこういう病気が起こっているのだろうと考えました。英語でlunar(ルナー)は「月の**」という意味ですが
lunatic(ルナティック)になると「精神異常の、発狂した」という意味になります。日本でも
うどんの食べ方によって キツネ憑(つ)きになる、という話を聞いたことがありますか?
「きつね」うどんと「月見」うどんをいっしょに食べると「キツネ・ツキ」だとか。
-
発見者
2021年9月15日|院長ブログ
健康維持にジョギングをしています。
10年くらい前の話。いつものジョギングをしていた時のことです。
 町外れの民家のガレージの前を通りかかりました。
町外れの民家のガレージの前を通りかかりました。中に目をやるとなんとガレージの中で人が倒れているではありませんか!
50代とおぼしき男、ついさっきまでガレージで何か仕事をしているような格好で、横向きに倒れており、
傍らの自転車も倒れていて、
つい今しがた倒れた、と自分の目に映りました。
周りには人がおらず、自分が第一発見者かもしれない。
私は男に近づいて、「大丈夫ですか?」と声をかけてみました。
男はちょっと薄目を開けたものの、再び目を閉じ、そのまま呼びかけに反応しません。
その瞬間、自分の中の医者としてのプロ意識が目を覚ました。
「救急のABC」のフローチャート! 頭の中を駆け巡りました。
脈、呼吸、体温をチェック。
呼吸と心拍は保たれている、意識がない。
瞳孔は左右対称、4ミリ。脳梗塞か脳内出血か??
胸をドキドキさせながら、とにかく人を呼ばねば、
と隣にあるお店に入っていきました。
(あんずクリニックの医師、ジョギング中に意識不明の男性の命を救う!)
などと翌日の新聞に出るかな、と自分の中に功名心がチラッと見え隠れしました
隣の店に入っていって、奥で座っていたオジサンに
「すいません、隣のガレージで人が倒れて意識不明なんですけど」
と声をかけたのですが、
オジサンは全然動じることなく、
「いいんですよ。酒飲んで酔っ払って寝てるだけですから。放っておいてください。」
と言われてしまいました。
その店の人は一応、確認のために面倒臭そうに店を出てきましたが、
倒れていた男は、私達が騒いでいるのがわかったのか、
「ん ああああ・・・」と
意味不明の声をあげ、寝返りを打ちはじめました。
酒臭い。










