院長ブログ
-
おやつ作ってみた
2025年12月14日|院長ブログ
おやつも食べたいし、ヘルシーなもので・・・
と考え、

自作のイモです
畑でとれたサツマイモを使ってフライド(スイート)ポテトを作ってみようと思い立ちました。
調理も楽しいです! 義務でなければ。

料理も気分転換になります
包丁で切って、揚げるだけ。
結果は・・・

黒砂糖と塩をふりかけ
「甘じょっぱい」味にしてみました写真のとおりですが、まあまあの出来でした。思いつきで作ったにしてはおいしかった。
外はコンガリ 中ホクホクという風にはなかなか行きませんでした。
さつまいもは畑で取れたものを放っておいて忘れてしまっていました(たぶん一か月くらい経過しているのでは)。
サツマイモは放っておけばおくほど甘くなる・・・と聞いていましたが、たいして甘くなかった。
揚げる油は何にする? 温度は? 揚げている時間は? 何をかけるとおいしい?
いろいろ試行錯誤しながら食べているうちに、食べ過ぎて腹が膨れて 夕ご飯食べられなくなってしまいました。
油と炭水化物だけで おなかパンパンです!
腹部膨満、キターーッ!
おなかが苦しい!
-
甘草&カンソウ
2025年12月10日|院長ブログ
11月の終わりに磐田市のマラソン大会があり、参加しました。
今年は私じつは60歳になりました。年齢なんて感じたくないのに、感じさせるものの一つが「参加者の年齢カテゴリー」で、大会パンフレットを見ると「ハーフマラソン」のカテゴリーの中に「20代~40代」「50代~」とか参加者が年齢別に記載されていますが、「60代以降」になると、がくっと、参加者の数が少なくなります。(40代の参加者が一番多かった)。
ちなみに、お客様アンケートとか答える時にも「50代~」から「60代~」にうつるのですが、今までよりショックが大きい。 たぶん自分の中で「50代まで→働く年代」「60代以降→リタイヤした人々」とカテゴライズしてしまっているせいもあります。
早く走ろうという意欲は年々減少していますが、ゆっくりだったら、最後まで走れそうな気がするので、今回のハーフマラソンも参加してみました。
マラソンしない人に言いますが、マラソンは、早く走ったら当然苦しいですが、ゆっくりだったら、楽しい気持ちになれます。エンドルフィンという脳内物質のせいとされています。ただし、マラソン大会中に幸福感を感じたことは、私はないです。
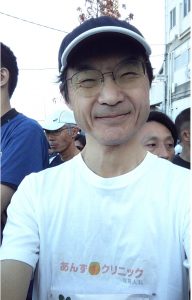
今回はお面をかぶってない
ジュビロスタジアムを出て、駅前の通りを走るころは、(後半のために体力を温存して・・・)と考えていたのですが、駅南から、福田方面に走っている間に、余力がなくなってきました。
このあたりまで、同じスピードで走っていた人に、ジリジリと差をつけられ、だんだんと背中が遠くなっていくのを見るのはつらい・・・
最後御厨駅前の坂を上っている頃なんて、ほぼ止まりそうでした。
なんでこんなに思うように体が動かないんだろう!
ゴールして思ったのは、(ああもっとちゃんと練習しとけばよかった・・・)。
*
私は練習不足もあって、走った後筋肉痛になりそうだったのですが、予防にのんだ漢方薬の「芍薬甘草湯」はよく効きました。
筋肉のけいれんや筋肉痛に効果がありますが、この成分の「甘草(かんぞう)」は読んで字のごとく甘いのです。英語でリコリスと言って、昔からお菓子に使われていましたが、胃薬や風邪薬としても昔から使われ、医療現場では肝臓の機能改善薬としても使われます。分子構造が副腎皮質ホルモンと似ているので、ステロイドと似たような作用があります。
妊娠中にもこむら返りを経験する人は多いのですが、この芍薬甘草湯が効きます。生理痛にも効きます。子宮の筋肉の緊張を取ります。
「シャクヤク・カンゾウトウ」と呼びますが、漢方薬の中ではシンプルにシャクヤク(芍薬)とカンゾウ(甘草)だけのセットです。
読み方が似ているだけなのですが、ちょっと前「カンゾー先生」という映画がありました。戦時中のある開業医の話で、どんな病気でも「肝臓炎」と名付けてしまう医者を揶揄してつけられた名前です。
私の婦人科の診察でも、一般の人にわかりやすい表現をしようとすると「ホルモン・バランスの乱れ」と言って片付けてしまうのですが、じつは専門家の間ではこういう言い方をしないので、これって「カンゾー先生」と同じレベルだなあ、と反省の気持ちを伴って感じます。
マラソンのほうはなんとか完走(かんそう)できました。
完走・先生でした。
-
聴覚スクリーニング検査
2025年12月7日|院長ブログ
聞こえることが当たり前の世界に住んでいる私たちには、音が聞こえていない人の日常はドラマでしか知ることができません。
ちょっと前に新生児の聞こえ(聴覚)の検査について、オンライン研修会があり参加しました。
研修会冒頭で、自分の経験を語ったのは聴覚障害で生まれて、人工内耳の手術を受け、健常者と同じ高校で生活できるようになった女の子でした。
印象的だったのは「私の母は、(聴覚障害があるとわかった)娘の手術を勧められたときに、音が聞こえない事もこの子の特性として受け入れ、手術をせずに生きてもらうことも考えた、だけど、将来、娘が大きくなった時に自分で「聞こえる世界」と「音のない世界」を選べるようにしておいた方がいいと思った、という理由で娘に手術をする決断をした」そうです。
難聴を「障害」ととらえず「個性」として受け入れて生きようという考え方もたしかにあります。

ただし治療(手術)を始めるなら、早ければ早いほど良いそうで、そのためのスクリーニング検査の精度も高い方がよいそうです。
普通に生まれる赤ちゃんのうち、1000人に1人くらいは先天性難聴が見つかります。
先天異常は妊娠中のエコーの検査で見つかるものもありますが、難聴は出生前にエコーでは診断できません。
研修会の後半では、日本語を流暢に話すアメリカ生まれの研究員(男)が、先天難聴で生まれたの娘の治療のため必死になって情報を探した苦労話やその経験からスマホアプリを開発した話を伺いました。私の個人的な感想ですが、自分の娘のためならオトーサンは何でもするよ、みたいな娘への愛情と、外国人にはわかりにくい日本の検査体制のしくみに必死で戦っている真剣さに感動しました。
ただし、(おそらく今回初の)Zoom配信による研修会のためか、いくつか小さなトラブルは絶えませんでした。
演者の画像だけうつっているのに、全く音が伝わっていない時間があったり、突然「ぽーーーーーッ」と大きな電子音がスピーカーから流れたり、演者のパソコンのマイクと会場のマイクが二重に音声をひろっていて、ハウリングしていたりと、
研修の話を聞いている私には、一昔前の補聴器のような音にも聞こえました。
トラブルの間、自分が難聴になったようでした。
こんなごちゃごちゃした音を聞かせられているのだったら、やっぱり音のない世界のほうが静かでいいかもしれない・・・
-
アフガニスタンの12月
2025年12月3日|院長ブログ
12月らしく寒くなってきましたね。
私、開業するずっと前は海外に出ることも多かったのですが、今回はアフガニスタンにいたころのことをお話します。
2002年4月から一年、アフガニスタン北部にNGOの医師として滞在していました。
緯度は日本の北関東と同じですが、乾燥していて雨が少なく、気温の変化が激しいところです。
夏には40度以上になるようなところですが、この年、大きな寒波が来て12月にはマイナス11度まで下がりました。
水道管が凍ってしまい使えなくなり、ガスも来ない、電気も数日停電続きました。アフガンはインフラが貧弱です。
私たちは、朝や夜はろうそくやランタンの明かりを便りにし、昼は自家発電機を回して通信機器や事務機器を動かさないと日本との定時連絡もとれませんでした。
一般の家庭には電気製品があまりないのと、停電が頻繁に起こる生活に慣れていて、あまりパニックにはなっていませんでしたが、滞在間もない私たちにとっては大変でした。
私は95年の阪神大震災で、冬季に電気や水、ガスの止まった状態で生活したことがありますが、アフガニスタンの方が過酷だった。
この状況を情報発信するメディアがないので、ニュースにならないだけですが、こういう寒さで絶対数十人単位で人が死んでいるはずです。
_

左端が私 アフガン人スタッフたちと(日本人3人)
アフガンで開設した診療所で患者をみていましたが、夏はマラリアや下痢が多い一方で、冬になると風邪や肺炎など呼吸器系の病気が増え、火を使うことが多いため、火傷の患者も多くなりました。馬に蹴られてケガをした人も冬季に多くなりました。
病気の人を治すよりも、自分が病気にならないようにするのが大変でした。
アフガンのこういう状況を経験すると、日本に帰ってきて、普通に暮らせることのありがたさをしみじみ感じます。
公園の蛇口から水が出る、停電しない電気がある。こんなことすら、うれしいのです。
-
逆子と出産
2025年11月30日|院長ブログ
おなかの中の赤ちゃんの位置で「逆子」というのを聞いたことあるでしょうか?
赤ちゃんは産まれる時に頭から出てくるので、出産前には赤ちゃんは頭が下になるのですが、お尻が下になっている赤ちゃんのことを逆子とか骨盤位と言い、医療現場では「ベッケン(ドイツ語由来)」とか「ブリーチ(英語)」とも呼びます。

骨盤位
なぜか最近うちで逆子の妊婦さんが多く、帝王切開のスケジュールをどうするか、ちょっと困っています。基本は帝王切開が勧められます。
逆子をなおすための方法として、逆子体操が昔勧められていましたが、逆子体操は現在ではエビデンスがないとされています。逆子のツボも知られているのですが、精度の高いエビデンスはありません。
おなかの外側から胎児を押して、頭が下になるように強制する方法があり、外回転術と呼びますが、条件が合えば行っています。
帝王切開をしないとどうなるかというと、お尻や足から赤ちゃんが産まれてきます。だいたい正常に産まれますが、中には頭が最後にひっかかって、その後の発育に障害が出る赤ちゃんもいます。赤ちゃんが問題なく産まれる確率を100%に近づけるために、20世紀に入ってからは「逆子は帝王切開」が常識となりました。産科医の中でも私の世代が、逆子を経腟分娩(下から産む)させる技術を知っている最後の世代です。
長年産科の医者をしていると、信じられないような光景を目にすることが多々あります。
私が病院勤めの勤務医の頃、陣痛が来ていた妊婦を診察(内診)したところ、赤ちゃんの頭より先(膣の方)に手の拳(こぶし)が触れたことがあります。産道の中で手が先に出てきてしまうと、赤ちゃんの体が産道にひっかかって通れないので、帝王切開をしないと産まれない、というのが常識でした。
現場の助産師や若手のドクターが慌てて、「早く!緊急の手術だ!」と右往左往している中で、私は「いや待て、慌てるな、下から産まれるかもしれないからもうちょっと様子を見よう」と言いました。
その産婦が前回出産したときにすごく安産だった事、診察してみると産道が普通の人より広く、赤ちゃんもそのまま出て来れそう(な気がした)だったからです。一対多数の意見で手術をしたほうがいい、ということになり、その産婦は手術室に運ばれて行きましたが、なんと帝王切開を始める直前の手術台で、下から赤ちゃんが産まれました。元気な赤ちゃん。
助産師は「先生がそんなにノロノロしてるから、カイザー(帝王切開)間に合わなかったじゃないですか!」と激怒している一方、
私は「だから帝王切開しなくていいって言っただろう!」(結果論なのは知ってますが、私も意地になっていたので)
と普段は温厚なスタッフの間で大ゲンカになりました。
おそらく一番不安だったのは、出産する当の産婦で、「帝王切開しないと赤ちゃん死んじゃう」と言われて動揺したはずです。
後で本人が私に笑顔で語ってくれたのは「この子の名前、拳(けん)君にしました。」ということでした。拳が先に出てきたからだそうです。
世の中を見回すと、これ以上に奇跡的な出産がいろいろあって、その最たるものはシャム双生児とか結合双生児と呼ばれるものです。
双子で、胴体や下半身がくっついて産まれてくる先天異常です。20世紀初頭から世界のあちこちで報告がありますが、帝王切開もできない時代、どうして下からあのような状態で産まれたのか、とても不思議です。
お産の世界は不思議なことがたくさんあります。
-
健康診断
2025年11月26日|院長ブログ
先日 一年に一回の健康診断を受けてきました。
シモの話で申し訳ないのですが、今回生まれてはじめて「2日続けて検便の検体が取れ」ました。
検診の検便では2日検便をすることになっているのに、ちゃんと取れたことがありませんでした。
もともと、私は2日くらい便が出ない体質だし、仕事柄精神的にストレスがあって、ちゃんと出ないことも多い。
身長・体重・腹囲測定で、変化している自分の加齢の現実を見せつけられました。
採血ですが、過去に自分のクリニックで働いていたスタッフに採血されたことがありました。
その人、自分の手が震えて、針が私の血管にうまく入らず、「他の人に代わってもらいます」と言って、私の面前で交代されたことがありました。
本人の都合で退職された方だったのですが、緊張するとうまくいかないんですかねえ。
*

胃カメラは「口からの」内視鏡の検査となりました。左側を下にしてベッドに横たわり、目の前のモニターに自分の体の中が映し出されるのを見ながら検査を受けました。
唾液を飲み込みたい衝動を我慢するのはつらいですが、普段見ることのできない自分の体の中が見れるのは面白いことでした。
胃の検査が終わり、カメラの視野が、胃の入り口から食道、咽頭、声帯をとおって、すぽっと抜けたときは、ほっとした気分になりました。
*
長い胃カメラのチューブが自分の体の中から抜けるのをみて、自分が子供の頃、ラーメンを遊びながら食べていたことを思い出しました。
インスタントラーメンを自分で作って食べていたのは、小学生の頃でした。
30㎝くらいのラーメンの麺をかまないようにして、端で片方をつまんで、飲み込む。
先端が胃のあたりに入ったと思ったところで、ラーメンの麺をそーっと引っ張ってきて、麺を全部出す。
なんてやっていたことを思い出しました。
-
11月の記念日
2025年11月23日|院長ブログ
「11月3日だから『いいおさん」だったね!」
11月3日に産まれた人にはそう言っていました。
さて、よく考えてみると、11月は「いい○○の日」とゴロ合わせできるので、記念日の多い月でしょうか?
探してみると あるわ あるわ・・・
11月03日 「いいお産の日」
11月05日 「いいりんごの日」「いいオトコの日」
11月07日 「いいオンナの日」
11月8日「いい歯並びの日」
11月10日「いいハンドクリームの日」(いい手の日) 「いいトイレ(10)の日」
11月11日 (1111の形状から沢山あります)
「ポッキー・プリッツの日」

ポッキーの11・11
「もやしの日」
「煙突の日」
「かりんとうの日」
「配線器具の日」(電源コンセントの差込口の形状が「1111」に見えることに由来)
「独身の日」(中国)
11月14日「アンチエイジングの日」(11・14→ いい トシとの語呂合わせで)
11月18日「雪見だいふくの日」アイスを作っているロッテが決めたらしいですが、18が雪見だいふくのパッケージをあけて縦に見た時に18に見えるから、だそうです
11月21日「かきフライの日」(11・21を「いいフライ」と読ませてますが、別にカキでなくてもいい気が)
11月22日「いい夫婦の日」
11月23日「いいツマミの日」(23でツマミと語呂合わせ)
11月26日「いいふろの日」「いいチーム(26)の日」
11月29日「いい服の日」「いい肉の日」
などなど、11月は「良い・・」とつくのでなんでも語呂合わせで記念日になります。
ちなみに私が制定するとしたら
11月03日 「いいオッサンの日」
11月31日「いい産院の日」
え? 11月に31日はないって・・・?
-
犬に逃げられた
2025年11月19日|院長ブログ
うちで犬飼っています。
柴犬です。
柴犬はクセがある。
私は子供の頃にも犬を飼ってましたが、純粋な柴犬を飼ったのは、これが初めて。
犬を分類したら「柴犬」と「その他の犬」に分かれるんじゃないかと思えるくらい、柴犬は個性的だと知りました。
散歩に行くか行かないかは、その時の気分で決まる。こっちが誘っても行かない時もある。
飼い主にしっぽ振らない。
芸覚えない。
散歩中突然ダッシュする。または突然立ち止まって、その場を動かない。

柴犬は突然ダッシュするので、軍手ではまずい。
このところ寒くなってきたので、手袋をしますが、安いので軍手で済ませています。
ただし、犬の散歩のときに軍手をしていると都合が悪いことに気づきました。
犬のリードを握る力が弱くなるので、犬が突然ダッシュすると、するっとリードが滑ってしまう。
これまで、軍手で散歩していて、3回、逃げられました。
柴犬なので、逃げたら最後、決して戻ってきません。
一回は、近所の家の庭で、他の家の人に向かって吠えているところを押さえつけて、戻しました。
一回は、追いかけるのをやめて、道のわきで、しょんぼりして座り込んでいるフリをして、油断して近づいてきたところをロープを踏んづけて、捕まえました。
一回は、30分くらい、どうやって追いかけても捕まらないので、あきらめて家に帰って寝ていたら、翌朝玄関に自分で戻ってきていました。おなかがすいたんでしょう。
指の出せる手袋を買ってみたら、よかったです。
しっかりロープがつかめるので、散歩には良いです。スマホもいじれるし。
クマも 犬も同様で、かわいいと思える部分はありますが、しょせん動物です。あまり感情移入はしないほうがいいかもしれませんね。
-
温度設定をめぐる葛藤
2025年11月17日|院長ブログ
職場の温度設定。
オフィスで仕事をしている人なら誰しも経験しますが、室温が「高すぎる」とか「低すぎる」と感じることはないですか? 市役所とか「夏は28度まで」と公表しているところは別ですが、決められた温度がなくて、リモコンの温度を上げたり・下げたり ってことはないですか?

冬場でもこれ以上暖かくしちゃダメだよな、という考え方の人もいる
夏場で、エアコンの設定温度もしょっちゅう変わる(というか、私はちょこちょこ変えている)のですが、冬場もよく変わります。コロナ後感染症対策には「換気をよく」するため、窓を開けるようになりました。
病院は病人のことを考えて、寒い時期には暖房がよく効いて暖かいのですが、総合病院などでは24度くらいまで上げているようです。
私のクリニックではいつもの冬は、病棟は24度、外来診察室の設定温度は22度くらいまでにしています。
先日は寒かった。
ヒューヒュー寒い風が入ってくる。
内診する場所で、下着をとった人のところにも風が入ってしまうので、申し訳ないと思いながら、でも感染予防も大事と思ってあえて窓を開けています。

冬場だったらこれくらい暖かくしなきゃ、と思っている人もいる
夏は夏で、冷房の効き目をどの程度にするか、はっきりした根拠はありません。
そうなると、エアコン温度の設定は、
1)中の人が快適と感じる温度
2)外気と温度差が大きすぎると健康によくないので、エアコンは効かせすぎない
3)節電も考える
などの要素のほかに
4)(うちのような医療機関では)患者(とくに新生児)のためには暖かめにしておく
(どの程度が暖かめか、は人によって意見が違う)
5)発言権の大きいスタッフが決める
6)リーダー(つまり院長である私)が決める
など種々の要素があります。
私の考えは、なるべく外部環境(自然)に近い状態で身体機能を損なわない程度にしたいのですが、たぶん全体の意見の総和ではない。
暖房の効きすぎたところ、冷房の効きすぎたところに長時間いると、体の自律神経機能に影響がでる、と心配しているのは私だけなのかどうか、自説を主張できる根拠もありません。あからさまにやると「この院長はいちいち温度にうるさい」と思われるので一人の時にちょこちょことリモコンの温度設定を変えたりしています。
リモコンの温度設定、
上がっていたら・下げる 下がっていたら・上げる
上がっていたら・下げる 下がっていたら・上げる
上がっていたら・下げる 下がっていたら・上げる
・・・
延々とやっています
-
人間ドック
2025年11月12日|院長ブログ
「人間ドック」という言葉を聞いたアメリカ人は
人間が鎖につながれて波止場にプカプカ浮かんでいるところを想像してしまうという。ちなみにDockといえば港の船着き場のこと,
「人間ドック」は和製英語で、日本でだけ使われている言葉らしいです。これではドザエモン(川に浮かんでいる水死体)じゃないですか、と一人でウケてます。
「人間ドッグ」と問診票に書いてくる人もいますが、これでは人面犬ですね。
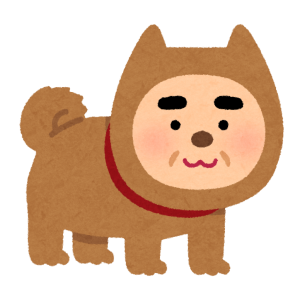
婦人科で行なっている健康診断(いわゆる検診)には子宮頚部がんがあります。
子宮頸(部)がんの検査も、単に細胞をとって終わり、という検診から、内診(双手診)で子宮卵巣の大きさに異常がないか調べる検診、エコーも併用する検診など様々あるのはご存じでしょうか。(今うちではエコーを併用したがん検診をしています。)
私が若いころ、アルバイトで「バス検診」に行ったことがあります。
バスの中に二つ内診台があって、カーテンの向こうから、交互にお尻が出てくるのです。
スピードは速いのですが、検査する私は、狭いバスの中、ずっと中腰を強いられ、しかも異常があるのかないのか、
ちゃんと内診もできないので非常にストレスで疲れるアルバイトでした。
膣の大きさもかなり個人差があって、お産の経験のある人に使う膣鏡をお産の経験のない人や帝王切開のお産の人にそのまま使うと痛みを伴うことがあり、神経使います。
*
卵巣がんの腫瘍マーカー(ガンがあると上昇する血液中の物質)を調べているところもあります。
子宮体がんの検査は、偽陰性といって、見落としの確率があるので、健康診断のスクリーニングには適していません。
以前は婦人科では子宮がん検診といっしょに乳がん検診もしているところが多かったです。
乳がんの検査は、現在では精度管理の点で触診よりはマンモグラフィーや超音波検査が勧められます。
さて昔は私も乳がん検診で触診をしていましたが、あるおばあちゃんの検診をしていた時のことです。
「わしみたいに70過ぎても乳ガンの心配することあるんですかセンセ?」とおばあちゃん。
「定期的にみたほうがいいですよ。どっかの牛乳みたいに、定期検査しないでほっといたら問題になることもありますから。」
当時、某牛乳会社が、賞味期限切れで汚染された牛乳を販売して問題になった頃の話です。

「わしの乳はもう賞味期限切れてるわ。ふぉっ、ふぉっ、ふぉっ」










