院長ブログ
-
11月の記念日
2025年11月23日|院長ブログ
「11月3日だから『いいおさん」だったね!」
11月3日に産まれた人にはそう言っていました。
さて、よく考えてみると、11月は「いい○○の日」とゴロ合わせできるので、記念日の多い月でしょうか?
探してみると あるわ あるわ・・・
11月03日 「いいお産の日」
11月05日 「いいりんごの日」「いいオトコの日」
11月07日 「いいオンナの日」
11月8日「いい歯並びの日」
11月10日「いいハンドクリームの日」(いい手の日) 「いいトイレ(10)の日」
11月11日 (1111の形状から沢山あります)
「ポッキー・プリッツの日」

ポッキーの11・11
「もやしの日」
「煙突の日」
「かりんとうの日」
「配線器具の日」(電源コンセントの差込口の形状が「1111」に見えることに由来)
「独身の日」(中国)
11月14日「アンチエイジングの日」(11・14→ いい トシとの語呂合わせで)
11月18日「雪見だいふくの日」アイスを作っているロッテが決めたらしいですが、18が雪見だいふくのパッケージをあけて縦に見た時に18に見えるから、だそうです
11月21日「かきフライの日」(11・21を「いいフライ」と読ませてますが、別にカキでなくてもいい気が)
11月22日「いい夫婦の日」
11月23日「いいツマミの日」(23でツマミと語呂合わせ)
11月26日「いいふろの日」「いいチーム(26)の日」
11月29日「いい服の日」「いい肉の日」
などなど、11月は「良い・・」とつくのでなんでも語呂合わせで記念日になります。
ちなみに私が制定するとしたら
11月03日 「いいオッサンの日」
11月31日「いい産院の日」
え? 11月に31日はないって・・・?
-
犬に逃げられた
2025年11月19日|院長ブログ
うちで犬飼っています。
柴犬です。
柴犬はクセがある。
私は子供の頃にも犬を飼ってましたが、純粋な柴犬を飼ったのは、これが初めて。
犬を分類したら「柴犬」と「その他の犬」に分かれるんじゃないかと思えるくらい、柴犬は個性的だと知りました。
散歩に行くか行かないかは、その時の気分で決まる。こっちが誘っても行かない時もある。
飼い主にしっぽ振らない。
芸覚えない。
散歩中突然ダッシュする。または突然立ち止まって、その場を動かない。

柴犬は突然ダッシュするので、軍手ではまずい。
このところ寒くなってきたので、手袋をしますが、安いので軍手で済ませています。
ただし、犬の散歩のときに軍手をしていると都合が悪いことに気づきました。
犬のリードを握る力が弱くなるので、犬が突然ダッシュすると、するっとリードが滑ってしまう。
これまで、軍手で散歩していて、3回、逃げられました。
柴犬なので、逃げたら最後、決して戻ってきません。
一回は、近所の家の庭で、他の家の人に向かって吠えているところを押さえつけて、戻しました。
一回は、追いかけるのをやめて、道のわきで、しょんぼりして座り込んでいるフリをして、油断して近づいてきたところをロープを踏んづけて、捕まえました。
一回は、30分くらい、どうやって追いかけても捕まらないので、あきらめて家に帰って寝ていたら、翌朝玄関に自分で戻ってきていました。おなかがすいたんでしょう。
指の出せる手袋を買ってみたら、よかったです。
しっかりロープがつかめるので、散歩には良いです。スマホもいじれるし。
クマも 犬も同様で、かわいいと思える部分はありますが、しょせん動物です。あまり感情移入はしないほうがいいかもしれませんね。
-
温度設定をめぐる葛藤
2025年11月17日|院長ブログ
職場の温度設定。
オフィスで仕事をしている人なら誰しも経験しますが、室温が「高すぎる」とか「低すぎる」と感じることはないですか? 市役所とか「夏は28度まで」と公表しているところは別ですが、決められた温度がなくて、リモコンの温度を上げたり・下げたり ってことはないですか?

冬場でもこれ以上暖かくしちゃダメだよな、という考え方の人もいる
夏場で、エアコンの設定温度もしょっちゅう変わる(というか、私はちょこちょこ変えている)のですが、冬場もよく変わります。コロナ後感染症対策には「換気をよく」するため、窓を開けるようになりました。
病院は病人のことを考えて、寒い時期には暖房がよく効いて暖かいのですが、総合病院などでは24度くらいまで上げているようです。
私のクリニックではいつもの冬は、病棟は24度、外来診察室の設定温度は22度くらいまでにしています。
先日は寒かった。
ヒューヒュー寒い風が入ってくる。
内診する場所で、下着をとった人のところにも風が入ってしまうので、申し訳ないと思いながら、でも感染予防も大事と思ってあえて窓を開けています。

冬場だったらこれくらい暖かくしなきゃ、と思っている人もいる
夏は夏で、冷房の効き目をどの程度にするか、はっきりした根拠はありません。
そうなると、エアコン温度の設定は、
1)中の人が快適と感じる温度
2)外気と温度差が大きすぎると健康によくないので、エアコンは効かせすぎない
3)節電も考える
などの要素のほかに
4)(うちのような医療機関では)患者(とくに新生児)のためには暖かめにしておく
(どの程度が暖かめか、は人によって意見が違う)
5)発言権の大きいスタッフが決める
6)リーダー(つまり院長である私)が決める
など種々の要素があります。
私の考えは、なるべく外部環境(自然)に近い状態で身体機能を損なわない程度にしたいのですが、たぶん全体の意見の総和ではない。
暖房の効きすぎたところ、冷房の効きすぎたところに長時間いると、体の自律神経機能に影響がでる、と心配しているのは私だけなのかどうか、自説を主張できる根拠もありません。あからさまにやると「この院長はいちいち温度にうるさい」と思われるので一人の時にちょこちょことリモコンの温度設定を変えたりしています。
リモコンの温度設定、
上がっていたら・下げる 下がっていたら・上げる
上がっていたら・下げる 下がっていたら・上げる
上がっていたら・下げる 下がっていたら・上げる
・・・
延々とやっています
-
人間ドック
2025年11月12日|院長ブログ
「人間ドック」という言葉を聞いたアメリカ人は
人間が鎖につながれて波止場にプカプカ浮かんでいるところを想像してしまうという。ちなみにDockといえば港の船着き場のこと,
「人間ドック」は和製英語で、日本でだけ使われている言葉らしいです。これではドザエモン(川に浮かんでいる水死体)じゃないですか、と一人でウケてます。
「人間ドッグ」と問診票に書いてくる人もいますが、これでは人面犬ですね。
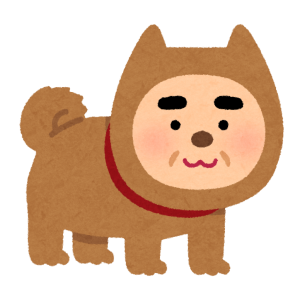
婦人科で行なっている健康診断(いわゆる検診)には子宮頚部がんがあります。
子宮頸(部)がんの検査も、単に細胞をとって終わり、という検診から、内診(双手診)で子宮卵巣の大きさに異常がないか調べる検診、エコーも併用する検診など様々あるのはご存じでしょうか。(今うちではエコーを併用したがん検診をしています。)
私が若いころ、アルバイトで「バス検診」に行ったことがあります。
バスの中に二つ内診台があって、カーテンの向こうから、交互にお尻が出てくるのです。
スピードは速いのですが、検査する私は、狭いバスの中、ずっと中腰を強いられ、しかも異常があるのかないのか、
ちゃんと内診もできないので非常にストレスで疲れるアルバイトでした。
膣の大きさもかなり個人差があって、お産の経験のある人に使う膣鏡をお産の経験のない人や帝王切開のお産の人にそのまま使うと痛みを伴うことがあり、神経使います。
*
卵巣がんの腫瘍マーカー(ガンがあると上昇する血液中の物質)を調べているところもあります。
子宮体がんの検査は、偽陰性といって、見落としの確率があるので、健康診断のスクリーニングには適していません。
以前は婦人科では子宮がん検診といっしょに乳がん検診もしているところが多かったです。
乳がんの検査は、現在では精度管理の点で触診よりはマンモグラフィーや超音波検査が勧められます。
さて昔は私も乳がん検診で触診をしていましたが、あるおばあちゃんの検診をしていた時のことです。
「わしみたいに70過ぎても乳ガンの心配することあるんですかセンセ?」とおばあちゃん。
「定期的にみたほうがいいですよ。どっかの牛乳みたいに、定期検査しないでほっといたら問題になることもありますから。」
当時、某牛乳会社が、賞味期限切れで汚染された牛乳を販売して問題になった頃の話です。

「わしの乳はもう賞味期限切れてるわ。ふぉっ、ふぉっ、ふぉっ」
-
亜鉛足りてますか
2025年11月9日|院長ブログ
食生活に亜鉛足りてますか?
生きていくのに必要な栄養はカロリー、たんぱく質だけではありません。
微量元素といって、鉄やマグネシウムなどとともに亜鉛も重要。
体内の含有量でランキングすると1位が鉄、2位が亜鉛 3位が銅(メダルのようです)で、亜鉛は意外と多く、体内に2.2g程度あります。
亜鉛が足りないと、味覚が低下します、若い世代の中に味が感じられないという人が増えていますが、かたよった食事による亜鉛の欠乏が原因です。
またケガが治りやすいかどうかも亜鉛が関係している。亜鉛華軟膏は皮膚の傷に使われ皮膚炎の治療に使われます。しもやけにも効果あり。
免疫力を維持するのに重要な元素で、髪や肌を健康に保ちます。
精力をつけるためにカキ(牡蠣)が良いと言われますが、カキは亜鉛を豊富に含んでいて亜鉛は精子の形成に欠かせません。
亜鉛を含む食品は他にも牛肉、卵黄、チーズにもありますが玄米や海苔にも少し含まれています。海苔を食べてカキの亜鉛を取ろうとしたら牡蠣1個に対して海苔180枚を食べる必要があり、とても太刀打ちできません。

牡蠣はおいしいですね。
カキ(牡蠣)の身はぶよぶよして見た目気持ち悪いから敬遠する、と言う人もいますが、やわらかくて旨味たっぷり、塩味もついていて、私は大好きです。
「牡蠣フライは哀(かな)しい味がする」って言っていた人(文学者)もいました。
このセリフ、詩的でいいなあと記憶に残っています。
英語圏では「オイスター(牡蠣)は”R”の付く月以外には食べるな」と言われています。Rのつく月というと September(9月)からApril(4月)までです。ちょうど夏場は牡蠣の産卵の時期で味わいが低下するから、という理由と、夏場は腸炎ビブリオなど食中毒のリスクが高くなることから そういわれるようになったようです。
牡蠣についてのこういうウンチクを、昔、女の子を食事に誘った時に、披露していた事もありましたが、先に自分が酒に酔っ払ってしまうのが常で、デートは失敗ばかりでした。
-
最近の同窓会
2025年11月9日|院長ブログ
先日、中学校の同窓会があり出席しました。
中学校の頃は、私が「学校の成績が良い」という理由だけでイジメられたこともありました。
今まで、あまり出席したい気持ちはなかったのですが、最近心境が変わりました。
卒業から年数が経つと、いじめられたことなど、どうでもよくなりました。
私たちの年齢になると、子育ては終わって、もうすぐ退職する年齢でもあり、旧交を温めたい人が多いのかもしれません。
中学のときの卒業文集が展示してあって、自分の書いたところもありました。
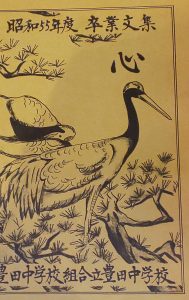
自分の書いたものははずかしくてお見せできません
恥ずかしいので見せません。
このブログを書いている人間とは別人格の人間が書いたような内容でした。
工場勤務の人、自営業の人、何やっているかよくわかんない人。生きているだけで、よかった。
高校や大学の同級生と比較すると、中学は自分と違う人がたくさんいて、面白いです。

中学校に進学する親がいて、公立か私立か迷っている人がいたとしたら、私は公立を勧めます。
-
ショウガは役に立つ!
2025年11月6日|院長ブログ

これは生姜でしょうが
寒い季節になると、ショウガを目にすることが多くなります。
ショウガ湯、ショウガ入りアメ、ショウガ風味の菓子。
ジンジャー・エール、ジンジャーブレッド、いろいろありますね。
「体を温める」として日本では知られていて、
冷え性に効果があるといわれています。
効能を信じている私は、ジンジャラー(生姜の信奉者をこう呼びます)の一人です。
東洋医学でも生のショウガを「生姜(しょうきょう)」、乾燥させてショウガを「乾姜(カンキョウ)」と呼びそれぞれ違う作用と呼ばれ漢方薬として使われます。
古代ギリシャの薬の本にも記載されており、欧米でも古くからハーブとして知られています。
イギリス国王ヘンリー8世がペストの予防に役立つとして国民に広めたのがきっかけで、ジンジャーブレッドが食べられるようになったとか。
ショウガの成分にはジンゲロールなどが含まれ、血行改善、体を温める作用があるとされています。成分の一つジンゲロンは基礎代謝を高めて脂肪の燃焼を促進するダイエット効果も知られています。
そのほか、殺菌効果があり、下痢の治療に使われたり、
蛋白分解酵素の働きのため、肉をやわらかくする働きもあります(豚肉のしょうが焼きはおいしいね)。
現在の欧米では乗り物酔いの吐き気止め、片頭痛、つわりの治療として役に立つとされていて、リウマチや関節炎などの治療にも用いられているそうですが、
なぜか
日本で広まっているように、体を温める効果についてはほとんど文献に記載されていません。
日本は神道の国で、神社(ジンジャー)があるからか?
ショウガない話ですみません。
-
裏側から見た富士山
2025年11月3日|院長ブログ
休日を利用して、山登りに行ってきました。
山道を歩いていると日常の雑事も忘れ、汗もかくし、気持ちも体も洗われるようです。
今回は山梨県の大菩薩嶺(だいぼさつれい)という山に登ってきました。
一般にはあまり知られていないかもしれませんが、「日本百名山」の一つで登山家の間では人気の高い山です。
前夜の夜9時に登山口の駐車場についてしまいました。ふもとに戻って宿泊のホテルを探すのも中途半端な時間だったので、
朝までクルマの中で車中泊をすることにしました。
たいして寒くならないだろうと、薄手の服と雨具だけ持参したのですが、標高1500mの登山口は、夜は2度まで気温が下がり、予想外の寒さにガタガタ震えてました。
クルマを停めた駐車場は30台くらい入るところで、自分が止めた時には自分の他に2台しか止まっていませんでしたが、
夜中にクルマが次々やってきて、夜が明けた5時半には駐車場はクルマでいっぱい。紅葉の時期、連休だからでしょうか。
朝6時というのに、登山口にも人が一杯。 登山口をすぎ歩き出しても、前にも後ろにも人、人、人。
たしか高尾山もこんなに混んでいたなあ、都心から近い低山の混み具合は、全然違う。
静岡県内にも同じくらいの高さの、名前の知られていない山がありますが、そういう山は、山頂に着くまで、全く人に会わない。
人が少ない山道はテンション上がります。遭難したら、帰れないので。
逆に人が多いとテンション下がります。

2000メートルを超える標高ですが、登り口が1500mくらいなのでズルした気分です
ただし、登山道から見える、紅葉の景色や、振り返って見える、雪をかぶった富士山の姿はすばらしく、やはり来てよかったと思いました。

静岡県民は「ウラガワの富士」と呼びます
山は良かったのですが、行きかえりに利用した、中部横断道、便利だけど、退屈な道で、なんとかならないかと思いました。
80㎞近く、ほぼ一車線で、前の車のテールランプを見て走ります。サービスエリアもない。スピードだせないし金魚のフン状態です。
-
漢方薬をよく出す診療科
2025年10月29日|院長ブログ
最近インフルエンザが流行しだしてますね。
インフルもコロナも、初期は鼻水や咳などの症状で、ふつうの「風邪」とみわけがつきにくい。
コロナの頃のように、マスクと手洗いが重要なのはかわりません。
さて、風邪をひくと市販の風邪薬を買ってのむ人が多いと思いますが、医師は風邪をひくと、市販の風邪薬ではなく漢方薬をのむ医師が実は多いです。
葛根湯は、風邪をひいたときによく使われる漢方薬です。

外科とか内科など診療科によって漢方薬をよく使う科とそうでない科があるのはご存じでしょうか。産婦人科は漢方薬を処方する頻度では一番多い科の一つです。
逆に整形外科とか眼科、生活習慣病をみる内科(循環器科等)は漢方薬をあまり処方しません。
「漢方薬なんてクスリじゃないよ」 と言っている医師もいます。
たしかに抗生物質や鎮痛剤 高血圧糖尿病などの薬は西洋薬にかないませんが、それ以外の領域ではよく効くものがあります。
婦人科では生理関係の体の不調、更年期症状、または自律神経の異常によく処方され、副作用も少ない。
葛根湯ばかり出す医者を「葛根湯医者」と落語のネタにされるくらい、葛根湯(1番)は何にでも使えますが、産婦人科医なら10種類以上は漢方薬のレパートリーがあります。
ただ処方する医者にとって時に面倒なのは「漢方を処方した時の保険病名」です。漢方薬には、効能が認められる病名がなければ保険診療(3割の患者負担)で使えません。
例えば 生理の量が多い過多月経や子宮からの不正出血。痔の出血で使われる「芎帰膠艾湯(きゅうききょうがいとう)(77番)」という漢方が効くのですが、過多月経には効能があるとされてないので患者のカルテには病名を「痔の出血」とつけなければ保険の審査が通りません。
痔ではない美しいご婦人を何人も「痔の持ち主」にしてしまったことに対して、良心の呵責を感じます。
婦人科でよく使う「加味逍遙散(かみしょうようさん)(24番)」の効能に「血の道症(ちのみちしょう)」という病名があります。私自身産婦人科の専門医になって、30年近く、現場で「血の道症」という病名を使ったことがありませんでした。(こんな非科学的な病名、使っていいんですか?)
「血の道」って何? 漢方薬の会社の人に聞いたところ、「女性の月経にともなう諸症状」という理解で差し支えないようでした。私が医者になる前の上の世代の漢方医がそのような病名を使っていたようです。現在よく話題にのぼる「月経前症候群(PMS)」や「更年期障害」(の一部)がこれに近いかと思われます。産後のマタニティブルーも「血の道症」らしい。女性特有の精神の変調 ということでしょうか。
血の道症の診断基準は産婦人科専門医の私も知りません。しかし加味逍遙散は更年期障害の気分の落ち込みによく効くので処方量が増えています。
私は(こんな、変な病名つけても保険審査に通してくれるのか)と思いながら「血の道症」の病名を付けて、保険申請することがあります。
返戻(カルテの審査で保険診療が認められず、請求元に突き返されること)はまだ、ありません。
-
ヒゲ
2025年10月26日|院長ブログ
あなたはヒゲの男性、どう思いますか?
昨今、ヒゲを生やしている男性を見かけるようになり、ヒゲが市民権を得てきています。

ラマダンの後のやつれた顔
私は20数年前、アフガニスタンに一年間住んでいたことがありますが、現地のイスラム社会では成人男性はヒゲをはやしているのが当たり前。
私もできるだけ現地の社会になじもうと、ヒゲを伸ばしました。 3週間もヒゲを剃らないでそのままにしておくと、段々とヒゲらしくなり
現地のスタッフたちは一様に 「おー、ドクター川島、カッコイイよお」
と誉めてくれました。 私はちっとも格好いいとは思いませんでしたが、みんなが誉めるので、しばらく続けてみました。
口ひげをたくわえてわかったことですが、夜寝るときなど、鼻息がヒゲにあたってわずらわしい。
トイレなどでこっそり鼻クソをほじった後(アフガンの街はホコリが多い!)や鼻をかんだ後でも、気がつかないうちに鼻クソがヒゲにこびりついていることがあり、(しまった!)と感じたことが数多い。
ミルクを飲んだ後でも、ミルクの白いのがいつまでもヒゲにこびりついていたこともありました。
毎週ヒゲをちょっとずつ刈りそろえないと、何もしない芝生のように、あっちこっちに向かってヒゲが伸びてきて手入れが面倒。
コップの水を飲むときに、水の中の大きなゴミをかき分けるフィルターの役目を果たすことはありましたが、それ以上の実用性はないことがわかり、すぐにヒゲをやめてしまいました。
アフガニスタンの男性どうしが出会うと、、まず握手ではじまります。 しかし、親しい間柄だと大の大人が男性同士で抱き合ったり、キスしたりします。
親しくなったアフガン男性に親愛の情を示されると、あごひげのジョリジョリ感が印象的です。










