院長ブログ
「清潔」という名のビョーキ
2021年6月30日|院長ブログ
治りにくいアトピー性皮膚炎、花粉症、アレルギー。
昔はほとんど存在してなくて、ここ数十年で患者がものすごく増えた現代の難病です。
どうも免疫がかかわっているらしい、という手がかりを寄生虫の感染から、世間に知らしめたのが、先日亡くなった藤田紘一郎という医学者です。
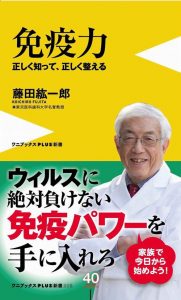
寄生虫となかよくして免疫をつけましょう、と説く人でした
寄生虫にたくさん感染しているはずの熱帯の子供たちには、アトピー性皮膚炎が一人もいないことから、寄生虫のいなくなった「清潔すぎる」日本の社会が、かえってよくないんじゃないか、と説いた人(衛生仮説と呼ばれます)で、熱帯医学を勉強していた頃の私には多大なインパクトのあった人でした。
今の日本では抗菌グッズが出回っているけれど、きれいにしすぎるのは問題ではないか、ということを最近までテレビに出演して、話をされていました。
私は90年代に藤田先生から話を直接聞く機会があったのですが、長崎大学の熱帯医学研究所で「熱帯医学研修」を受講した時です。
この熱帯医学研修には将来NGOやJICAなどの機関に入って途上国で働きたい人、大学で寄生虫を勉強したい人などが集まっていました。
熱帯医学というと何が思いつきますか?
マラリア、デング熱などが代表ですが、先進国ではすでに昔の病気とされてしまっている、結核やハンセン病もあり、途上国には薬が入りにくいHIV感染などもあります。熱帯医学研修とは熱帯特有の疾患、熱帯での体の変化、新興国の健康の問題など熱帯と医学に関係したいろいろなものを勉強できるコースでした。
研究所のスタッフの人たちも途上国や熱帯に関して「熱い」情熱を持った人たちで、心の純粋ないい人ばかりでした。
私も熱帯特有の寄生虫やウイルス疾患、その他熱帯病に関するいろんなことを学んだ「はず」ですが、
記憶に残っているのは、同じ研修生どうしで酒飲んだり、長崎の街でチャンポンを食べ歩いたり
「酷暑の環境で、生体の発汗量を調べる」という生理学の実験で、ネズミを使った実験がありました。
気温をどんどん上げて心拍や血流の変化を調べたのですが、やった後で宿題のレポートを
さぼって書かなかったので「ネズミを無駄に殺してしまって!」と教授に怒られたことだったり、
東南アジアからの留学生たちと宴会をやって、当時流行のマカレナ・ダンスを踊った、そんなことばかりです。
お金はなかったけど、夢だけはあって、いい時代でした。
その何年か後、私はアフガニスタンに1年間滞在することになりましたが、熱帯医学の知識がとても役立ちました。










